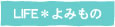


今回は私たち日本人の主食、お米のお話です。お米の銘柄ですぐに思い浮かぶものといえば「コシヒカリ」ですよね。特に、新潟県の魚沼地方で採れるコシヒカリは最高級ブランド米として知られています。ほかにも、「あきたこまち」、「ひとめぼれ」、「ヒノヒカリ」などがありますが、これらを含む人気のあるお米の品種のベストテンのうち9品種までが、コシヒカリの血を引いています。現在売られている電器炊飯器のおいしい炊き方の基準も、魚沼産コシヒカリに合わせてあるそうです。
これだけコシヒカリが不動の人気を保っているのはどうしてでしょう?
コシヒカリは、おいしいお米の4大要素と言われている「食味」「色」「つや」「粘り」のバランスが非常に良いお米なのです。でも、今でこそこんなに有名になったコシヒカリですが、かつては劣等性として見向きもされなかったんですよ。信じられないでしょう? というのも、コシヒカリは、稲にとっては大敵の「イモチ病」(茎や葉っぱを枯らして稲穂が実らなくなる病気)に弱い上、背丈が高いために倒れやすい為、今でも農家さんにとっては作りにくいお米なのです。唯一の特性が「おいしい」こと。長い年月をかけて生き延びた結果、現在のような高い評価を得るお米になったのです。学校では出来が悪かったけれど実は才能のある子だった……それがコシヒカリと考えると、なんだか親近感が湧いてきませんか。
ひと昔前にはコシヒカリと人気を二分するお米もありました。「ササニシキ」です。名前を聞いたことがある人もいるでしょう。コシヒカリに比べると、あっさりしていて香りがよく、今でも「寿司にはササニシキ」とお寿司屋さんたちに根強く支持されています。そのササニシキ、近頃復活の兆しが見えるものの、私たちの近所の多くのスーパーからは姿を消してしまいました。その理由は、コシヒカリが北海道と沖縄を除く東北から九州の至るところで作ることができるのに対して、ササニシキは、東北の一部でしか作ることができなかったせい。それに加えて、1980年以降冷害が続いて採れなくなってしまったこともササニシキの流通量が減った原因です。東北の農家さんたちは、次第に、ササニシキに換えて冷害に強く味のよい「ひとめぼれ」を作るようになっていったのです。

さて、お米そのもののおいしさは、お米に含まれる2種類のデンプン質、アミロースとアミロペクチンの量で決まります。アミロースができるだけ少なく、アミロペクチンが多いほうが粘りのあるおいしいお米になります。近年では、冷めてもモチモチ感が残るおいしいお米「低アミロース米」も開発されました。
でも、この人気の粘りのある甘いお米、「味がしつこくて苦手」、「日常食としては胃に重たい」という人もいるでしょう。そんな人たちに私がおススメしたいのが、自家製ブレンド米です。たとえば、ちょっと古くなったお米に低アミロース米や新米のコシヒカリのようなモチモチ感のあるお米を混ぜて炊きます。すると、ちょうどよいふっくらおいしいご飯になるんです。お米のブレンド技術といえばお米屋さんの得意技です。あなた好みの「ブレンド米」を、お米屋さんに相談しながら探してみるのもおもしろいかもしれませんよ。
<次回のリリースは12月11日。お楽しみに♪>
ページの先頭にもどる